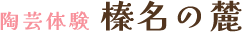器の色はどうやって決まる? 面白くて不思議な釉薬の話
陶芸体験で作られた器が、窯から出てきたときにどんな色になっているか、想像したことはありますか? 土の色は茶色や白っぽいものが多いのに、焼きあがった器には青や緑、黄色や、何とも言えない深みのある色が付いていますよね。この色の秘密こそ、「釉薬(ゆうやく)」というものにあるんです。
釉薬は、簡単に言うとガラスの粉のようなもの。これを素焼きした器の表面に塗ったりかけたりしてから、高温で焼き上げます。すると、釉薬が溶けてガラス状になり、器の表面をツルツルと覆ってくれるんです。このガラスの膜が、器を丈夫にして、水を通しにくくする役割も果たしてくれます。
そして、釉薬の一番面白いところが「色」です。釉薬には、鉄や銅、マンガンなどの金属の成分が含まれていて、これが焼き上げられる過程で様々な化学変化を起こし、色を生み出します。さらに不思議なのは、同じ釉薬を使っても、窯の中の温度や、炎の状態(酸素が多いか少ないかなど)によって、全く違う色に焼き上がることがあるんです! 例えば、銅の成分が入った釉薬は、焼き方によっては美しい緑色になったり、真っ赤な色になったりすることもあります。「窯変(ようへん)」と呼ばれたりする、まさに窯の中で起こる魔法のような現象です。
榛名の麓の陶芸体験では、志野茶碗で有名な岐阜の志野土を使い、釉薬には木灰を配合した日本伝統の釉薬を基本としています。これにより、市販の器ではなかなか見られないような、深みのある、そして一つ一つ表情の違う趣のある作品に仕上がります。当工房では、このこだわりの釉薬を八種類の中からお選びいただけます。
器の形を作るのも楽しい時間ですが、「この釉薬を選んだらどんな色になるかな?」と想像しながら待つのも、陶芸の大きな楽しみの一つです。ぜひ、榛名の麓で、器の色を決める不思議な釉薬の世界にも触れてみてください。どんな色に出会えるか、焼き上がりをどうぞお楽しみに!